----
サクラは、ソファでアイス(チョコモナカジャンボ)。
「……!?」
九門は再び机の方に体を向け、キーボードを叩き始めた。
サクラが見つめる九門の背中、「セーフ、セーフ」という声が聴こえてくる(気がする)。
カタカタカタカタ……。
「異世界バスケ」は55話まで進んでいた。
その数は、膨大だった。
この主人公は生まれつき素晴らしい才能を持っていたわけではなく、努力が実ったわけでもない。ずっと補欠として過ごし大人になった男だ。それは大多数の読者も同じである。学生時代に大きな実績を残してトップリーグに進むような選手は、600万近いバスケ人口のなかのごくごく一部だ。つまり、「自分がスーパースターだったら」は、何百万人の願望なのである。
いま、明らかにこのラノベはブームを迎えようとしている。
サクラと焼肉を食べながら、九門は思った。
週末の九門の部屋、
カタカタカタカタ…。
九門は一心不乱にキーボードを叩いている。ブログを始めたころと同じ勢い、いやそれ以上かもしれない。
サクラは、ソファでアイス(チョコモナカジャンボ)。
「大地くん、どしたん? また書きだして」
「ん?」
「最近ちょっと落ち着いとったのに」
「そーだったっけ?」
サクラ、少し小さめの声でつぶやく。
「あのときは、ぎょーさん話できたのに…」
「……!?」
九門、何か予感があったのか、突然振り返る。
「今日は焼肉でも食いに行くか」
サクラ、目を見開く。
「行く!!!」
「よし、じゃあ早く終わらせるよ」
「うん、お腹空いたけん早よしてえよ」
九門は再び机の方に体を向け、キーボードを叩き始めた。
サクラが見つめる九門の背中、「セーフ、セーフ」という声が聴こえてくる(気がする)。
「まいっか」
カタカタカタカタ……。
九門はキーボードを叩き続ける。仕事の時と同じ顔で叩いている。サクラが好きな顔だった。また会話量が減るかもしれない、と思いつつ、サクラは許した。
「異世界バスケ」は55話まで進んでいた。
主人公はまだダンクが出来ることを周囲には話していない。
だが、「ダンクが出来ること」と「自身の脳が26歳であること」が合わさり、プレイスタイルはどんどん変わっていった。練習で1対1の勝負を挑む場面が増えた。そして、その勝負を制すことが多くなった。
はたして「早く自分を試合に出せ」とアピールを始める。
この主人公のモデルは九門自身だが、その九門はバスケ部員だった少年時代、こんなプレイスタイルではなかった。試合に出る機会もほとんどなかった。「こんな選手でありたかった」という九門の思いが投影された主人公の躍動は、いよいよ読者の心を掴み始める。
多くの読者もどこかに願望があったのだ。「もし自分がスーパースターだったら」という願望が。
その数は、膨大だった。
現在の日本におけるバスケットボールの競技者登録人数、つまり部活動やクラブチームに所属するプレイヤーの数は約62万人。これはサッカーに次いで2番目に大きな数字である。さらに、サークルや草バスケなど何らかの形でバスケットボールをプレイしている「実施人口」は600万人近くにまで上る。観戦する競技としては野球やサッカーのような認知度はないものの、「バスケをやっている人数」は実は驚くほど多い。
そのうちの大多数が、前述の「願望を抱く」側の人間だと考えると――。
この主人公は生まれつき素晴らしい才能を持っていたわけではなく、努力が実ったわけでもない。ずっと補欠として過ごし大人になった男だ。それは大多数の読者も同じである。学生時代に大きな実績を残してトップリーグに進むような選手は、600万近いバスケ人口のなかのごくごく一部だ。つまり、「自分がスーパースターだったら」は、何百万人の願望なのである。
UFOにさらわれ小学生時代に戻るというハチャメチャなストーリーながら、多くの読者の願望を代わりに叶えているような九門のラノベは、その何百万のベースを持つ読者の心をドンドン掴んでいったのだった。
いま、明らかにこのラノベはブームを迎えようとしている。
サクラと焼肉を食べながら、九門は思った。
「面白いじゃん、ラノベ」
----
目次はコチラ
----
▼原文はコチラです
----

|


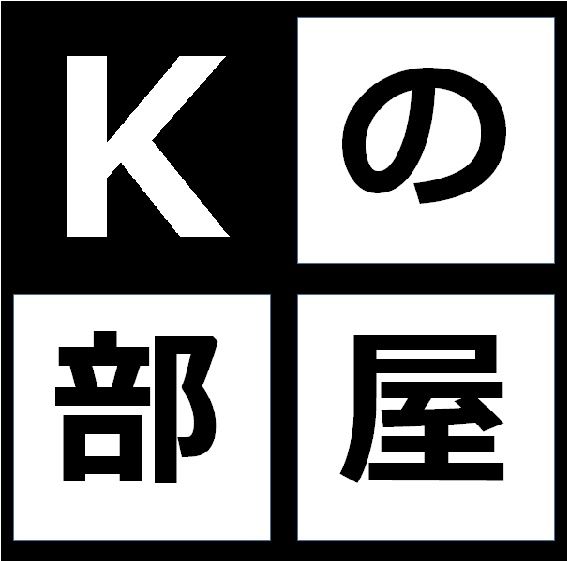
小説/僕のラノベは世界を救う 第17話/またのめり込んだ へのコメント一覧
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?